|
|
絵画:エリザベート・ヴィジェ・ルブラン 「デュ・バリー夫人の肖像」
Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, Madame Du Barry, 1781.
音楽:J・S・バッハ ブランデンブルク協奏曲第5番 BWV1050 第3楽章
J.S.Bach, Brandenburg Concerto No.5 in D, BWV1050, 3rd Mvt.
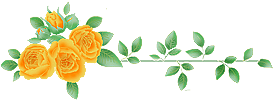
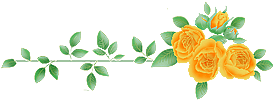
| マリー・アントワネットが皇太子妃時代に、宮廷で対立した、デュ・バリー夫人。 デュ・バリー夫人は、マリー・アントワネットの夫である王太子(後のルイ16世)の祖父、フランス国王ルイ15世の愛妾でした。  本名は、マリ・ジャンヌ・ベキュ(Marie-Jeanne Bécu)です。 ジャンヌは、1743年8月19日に、パリから東に250kmほど行った小さな町、ヴォークールールに、料理女(お針子という説も)アンヌ・ベキュの私生児として生まれました。 子連れでパリに出たアンヌは良縁を見つけ、娘ジャンヌを修道院寄宿学校に入れます。そこでジャンヌは9年間、教育を受けました。 15歳で修道院を出たジャンヌは、美容師見習い、次に裕福な婦人の奥女中となりますが、いずれも美貌が災いして首になります。 次に洋裁店で働き始めると、またたく間にその美しさは広まり、多くの富裕な男友達を作りました。その1人が、道楽者で、悪名高いデュ・バリー伯爵でした。 まもなくジャンヌは、デュ・バリー伯爵と暮らすようになりました。デュ・バリーはたいへんな食わせ者で、愛人であると同時に、ジャンヌの美しさを利用し、彼女を社交界に連れ出し、金持ちの貴族に周旋しました。 デュ・バリー伯爵は、どうしようもない道楽者でしたが、目は確かでした。ジャンヌは、上流階級の人々との、このような交際を通じて、礼儀作法や洗練された社交術を身につけていったのです。 そして、宮廷に出入りするまでになったジャンヌは、1769年に国王ルイ15世に紹介されました。王はたちまち、美しいジャンヌの虜となります。 この時、王58歳。ジャンヌは25歳でした。 ジャンヌを国王の正式な愛妾として宮廷に入れるため、デュ・バリー伯爵はジャンヌと、自分の弟を形だけの結婚をさせました。結婚をさせたのは、宮廷には、公式愛妾は、既婚夫人でなければならないという慣例があったからです。伯爵自身がジャンヌと結婚してもよかったのですが、妻子があったために、独身の弟を利用したのです。 こうして、国王の寵姫、デュ・バリー夫人が誕生したのです。
ジャンヌ・デュ・バリー夫人が、国王の愛妾となった1年後、オーストリアから皇女マリー・アントワネットが、国王の孫である王太子のもとへ嫁いできます。 マリー・アントワネットは、娼婦や愛妾が嫌いな母、女帝マリア・テレジアの影響を受け、デュ・バリー夫人を徹底的に嫌いました。 大嫌いなデュ・バリー夫人一言も口を聞かず、公然と無視し続け、デュ・バリー夫人に恥をかかせました。 デュ・バリー夫人も黙ってはおらず、マリー・アントワネットを“赤毛のちび”と呼んで罵倒し、容貌、言葉、しぐさなど、あらゆることを批判しました。 けれど結局、国王の愛人であるだけの立場の弱い、デュ・バリー夫人はこの状態に耐えられず、ルイ15世に「せめて言葉くらいかけてほしい」と泣きつきました。 かたくなに口を閉ざし続けたアントワネットですが、国王ルイ15世、そして母マリア・テレジアにまでいさめられ、1772年の元旦の、新年拝賀式にただ一言だけ、「今日のヴェルサイユは、たいへんな人ですこと!」と、デュ・バリー夫人に声をかけました。アントワネットが嫁いできてから、1年半の後のことでした。 確かに出自も経歴もよいとはいえないデュ・バリー夫人ですが、そんな境遇にありながら、国王の寵姫に登りつめた彼女は、やはり、人をひきつけずにはいられない美しさと魅力を持った女性だったようです。性格は、意外にも、暖かく朗らかで、親しみやすい、気立ての優しい女性だったと伝えられています。 1774年の4月に、ルイ15世が天然痘で倒れると、デュ・バリー夫人は、ヴェルサイユを追放され、にポン・トー・ダム修道院に幽閉されました。不遇な一時期を過ごしましたが、宰相ド・モールパ伯爵やモープー大法官などの人脈を使って、パリ郊外のリシュエンヌに戻り、優雅に過ごすようになりました。けれど、二度と、ヴェルサイユの宮廷に戻ることは、許されませんでした。 そして1789年にフランス革命が勃発し、4年後の1793年4月に、にデュ・バリー夫人は革命派に捕らえられ、同年12月、処刑されました。 |
|
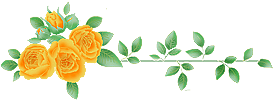
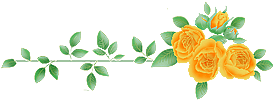
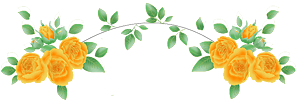
 |
 |